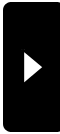2012年09月01日17:58
小水力発電による地域づくり≫
カテゴリー
去年書いたレポートですが、県民投票が現実化に向けて進んでいる今、再度掲載します。
代替エネルギーの一つに「小水力発電あり」です。
1.小水力発電とは
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、再生可能エネルギーへの関心が高まってきている。主流は太陽光や風力であるが、自然の川の流れや農業用水、上下水道などを利用して発電する「小水力発電」へも関心が高まってきている。「小水力発電」は、ダムなどの大規模な設備を必要としない出力の小さい発電(1000kW以下)で、水の流れと落差があれば、自然環境を大きく壊すことなく、発電が可能だ。発電機の種類も増えてきていて、様々な場所での導入されている。またさらなる導入計画もある。
小水力発電のメリットとしては、太陽光発電や風力発電と比べると、発電量が安定をしていて、身近な水路からも電気をつくれることができ、設備投資が太陽光発電や風力発電に比べると安くすむなどがあげられる。その反面、落差と水量のあることが必要条件のため、設置できる箇所が限られる、季節によって水量の変化があり発電量が変動するなどのデメリットがあげられている。
しかし、地域で生み出した電力をその地域で使う「エネルギーの地産地消」としても「小水力発電」は注目を浴びている。
代替エネルギーの一つに「小水力発電あり」です。
1.小水力発電とは
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、再生可能エネルギーへの関心が高まってきている。主流は太陽光や風力であるが、自然の川の流れや農業用水、上下水道などを利用して発電する「小水力発電」へも関心が高まってきている。「小水力発電」は、ダムなどの大規模な設備を必要としない出力の小さい発電(1000kW以下)で、水の流れと落差があれば、自然環境を大きく壊すことなく、発電が可能だ。発電機の種類も増えてきていて、様々な場所での導入されている。またさらなる導入計画もある。
小水力発電のメリットとしては、太陽光発電や風力発電と比べると、発電量が安定をしていて、身近な水路からも電気をつくれることができ、設備投資が太陽光発電や風力発電に比べると安くすむなどがあげられる。その反面、落差と水量のあることが必要条件のため、設置できる箇所が限られる、季節によって水量の変化があり発電量が変動するなどのデメリットがあげられている。
しかし、地域で生み出した電力をその地域で使う「エネルギーの地産地消」としても「小水力発電」は注目を浴びている。
2.岐阜県郡上市石徹白の取組
私は2007年から小水力発電の導入実験をし、あわせて持続可能な地域づくりを目指している岐阜県郡上市白鳥町石徹白(いとしろ)に調査に出かけた。説明していただいたのは、NPO法人地域再生機構理事の平野彰秀さん。

小水力発電の導入実験をしている「石徹白地区」は、岐阜県の福井県境にある、標高700メートルの盆地に位置する。縄文時代からの歴史を持ち、白山中居神社を中心とした白山信仰で栄えた村だ。明治まで神が仕える人が住む村として、どの藩にも属さず、年貢免除・名字帯刀が許され、独自に地域自治、文化を保ってきた。50年前には1200人ほどが住んでいたが、現在は1/4の約270人と過疎高齢化が進んでいる。

「なんとかしないと!」と危機感を持った住民たちは、2003年NPO法人やすらぎの里いとしろを設立し、「将来にわたっても、石徹白小学校を残すこと」を合い言葉に、地域課題解決に取り組んできた。持続可能な地域にしていくためには、「地域の自立」を目指し、地域産業づくりが必要と考え、小水力発電もその一環として、2007年から導入に向けて検討を始めてきた。石徹白には、白山に降る雪や雨の豊かな水量がある農業用水が張り巡っていた。冬は融雪、夏は野菜などの洗い場としても使われてきた、先人たちの遺産であるこの農業用水を活用して、水力発電に取り組んでいるのだ。
現在稼働しているのが、既存の農業用水沿いに導水路を設置し、そこにらせん型の水車をはめこんで発電するタイプ。この発電出力は、常時500W、最大800W。ここで発電した電気は、直流30V未満に変換し、道路を横断し、地元NPOの事務所の照明、冷蔵庫、テレビ等に使用されている。らせん型水車は、流量が多く、落差が低い場所に向いていて、ゴミがつまらないのが最大の利点だ。農業動力用として,以前は日本でも多く使われていた。設置費用は、約200万円。

現在、設置が完了し、稼働を待っているのが上掛け水車タイプ。これは、隣接する「白鳥ふるさと食品加工伝承施設(通称加工所)」の電力の一部を賄うために設置された。今後加工所は名産品のとうもろこしを使った加工品づくりに着手する予定だ。平野さんはこの水車を「地域の活性化のシンボルとしていきたい」と話す。出力常時750W、最大2200W。土木費用も含めて、設置費用約700万円。

石徹白地域では、将来電気軽トラを導入し、50Kw規模の発電所の設置をしたいと考えており、エネルギーの自給ができる地域を目指している。石徹白地域エネルギー自給可能性調査で、毎年およそ1200 万円が家庭での電気料金として、地域外に流出していることがわかった。車のガソリンや冬場の暖房の灯油などを含めるとエネルギー関連でさらに多くのお金が地域外に支出されている。そこで地域外にお金を流出させるのではなく、地域の資源を利用したエネルギー事業をつくることで今まで地域外に支出されていた金額、1200万円以上を地域に取り戻すことができるのではないかと地域では目論んでいる。
また、小水力発電の設置やメンテナンスは簡易な仕組みとなっているため、地域内の小規模事業者でまかなうことができ、地域の雇用にも寄与できる。例えば、上掛け水車タイプのブレード(はね)は、木製のため、万が一割れても、そこだけ取り替えれば済むことができる。
石徹白地域は小水力発電設置をきっかけとして、地域をあげた地域づくり、そして都市との交流が始まっている。具体的効果として、小水力発電を導入したことによって、小水力発電を目当てに石徹白に視察に訪れる人たちが増えたことだ。視察の際、活躍するのが「くくりひめ」という女性たちのグループ。(くくりひめの名前は、イザナギ命・イザナミ命が主祭神である白山中居神社の前にククリヒメの社があり、それにちなんで名付けた。くくりヒメは、イザナギとイザナミを仲直りさせたと言われる。調和と結合の神、和解の神、総てのものをくくり合わされるをご使命とされる仲直りの神様)。石徹白地域に住む女性たちが土地の旬の食材をバランスよく取り入れた、見た目、味も抜群なランチを提供する。小水力発電に視察に来た方々が、彼女たちのおもてなしと石徹白の自然や歴史に魅了され、石徹白ファンになっていっていくという。「地域ビジネスが地域ファンをつくり、地域ファンが地域ビジネスを支える」そんな実践モデルのひとつだ。ちなみに私と一緒に石徹白に視察に行ったひとりが石徹白をいたく気に入り、ちょうど募集をしていた加工所の求人に応募、子ども2人とともに家族で移住してしまった。また、今回説明をしていただいた平野さんも、石徹白の魅力にはまり、この秋から家族で岐阜市内から石徹白に引っ越しをしてくる予定だそうだ。「将来にわたっても、石徹白小学校を残すこと」という目標に石徹白に向かって、着実に向かっている。

3.小水力発電の全国の事例
現在、出力1000Kw未満の小水力発電は、長野、岐阜、富山などに約500カ所ある。京都市の嵐山、桂川の小水力発電所は、観光の名所渡月橋を渡る人々の足下を照らす照明のエネルギーとして供給されている。また、山梨県都留市では「小水力発電のまち」として、市役所前を通る家中川(かちゅうがわ)に開放型水車「元気くん」を設け、アピールしている。現在2台の「元気くん」が稼働中で、「元気くん」の電力は、日中は市役所の電力として使われ、市役所が閉庁する夜間や休日は、電力会社に売電している。平成21年度からは、「元気くん」が発電した電力に付加する「環境価値」を「グリーン電力証書」として、販売している
環境庁が2009年に実施した「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」によれば、1000kW未満の賦存量は、約629万kW(22,474カ所)となっている。参考までに、原子力発電1基は約100 万Kw。
そうした中で、環境モデル都市・長野県飯田市では、平成21年度環境省の小水力発電による市民共同発電実現可能性調査の委託を受け、いくつかの地点の水量や落差、発電設備の工事費や維持管理費のシュミレーション、年間発電量などを調査した。その結果、いくつかの有力な候補地が存在することはわかった。今後、環境調査とともに、地元住民の合意形成をはかっていき、事業化に向けて進めている。
また、新たな試みとして、市民出資で小水力発電事業を行う「立山アルプス小水力発電事業」が始まっている。小水力発電への市民出資事業としては、日本で初めてのものだ。市民のお金で日本国内の自然エネルギーを増やすことに取り組むおひさまエネルギーファンド株式会社が、富山県立山を水源とする小早月川の小水力発電所の設置への出資者を募集。発電で得られる収益の一部を出資者に分配金を還元していく仕組みだ。個人でも参加できることから、ひとりでは大規模で難しい自然エネルギーなどの導入や活用が、多くの市民の「意志ある出資」で、可能になっていく。志ある市民のお金「市民出資」により地域事業として実現することで、「21世紀の新しい地域 経済」の可能性を目指していく注目すべき動きだ。
4.小水力発電導入の課題
小水力発電の普及を妨げる要因の一つが、手続きの煩雑さだ。現状では、大型水力発電並の膨大な書類、手続きが必要だ。河川管理は国土交通省、農業用水は農林水産省、発電は経済産業省、などなど関係官庁がバラバラで、特に水利権の調整は煩雑だ。小水力発電を設置するための手続きの簡素化、規制緩和は急務だ。
「小水力発電」の水資源量1位の岐阜県と2位の富山県は、手を組んで、障害になっている水利権手続きの緩和などを国へ働きかける試みを始めている。また、岐阜県は、内閣府の総合特区に小水力を含めた新エネルギー振興に向けた総合特区の申請を予定している。
もう一つの要因が採算性だ。事業仕分けで国からの補助金が廃止されたため、初期投資に負担がかかり、せっかく事業を起こそうとしても二の足を踏んでしまう。現在、再生可能エネルギー法案が国会で審議されているが、小水力発電の売電価格は低く抑えられる可能性が高く、投資コスト回収ができるかどうか微妙なところだ。理想としては、小水力発電で発電した電力を長期間、発電に有利な価格で買い取ることを電力会社に義務づけることができるならば、小水力発電の普及が進んでいくことだろう。
しかし、設置の採算性だけを考えるのではなく、石徹白地域にように発電設備の設置や整備が地域の産業創出と見れば、新たな地域の収入源、雇用の確保が生じることとなる。小水力発電に適しているところは、水の落差がある山村や農業用水のある農村だ。いわゆる中山間地に、新たな地域産業が生まれることによって、働く場をつくり、地域住民の流出を防ぎ、新たな流入者を増やすことができる可能性も生まれる。
手続きや採算性の外部の課題とは別に、地域で「どこが主体としてなっていくか、どう主体を形成していくのか」という地域内部の課題も存在する。石徹白地域のケースでは、まず岐阜NPOセンターが「小地域のエネルギー自給モデルを構築するための実験・調査」をきっかけに石徹白に入っていった。当初、石徹白の歴史や文化を徹底的に調べ、様々な団体や寄り合いなどにヒアリングをして、地域性を理解していくところから取りかかった。そうした中で、NPO 法人やすらぎの里いとしろという地域再生に主体的に関わっている組織の存在と繋がり、協力体制をとる中で、調査段階から地域の方々と関わるようになっていった、しかし、住民全員が参加しているわけではないので、より多くの住民の理解を求め、事業を円滑に進めるために、自治会の会合において説明会を開き、自治会の賛同を得ることを心がけた。その後の様子は、上記で書いたとおりだ。そうした丁寧な主体づくりが「くくりひめ」「加工所」などの動きにつながっていった。
今後設置予定の飯田市でも、丁寧な地元説明会を開くとともに、あくまでも地域住民が主体であることを確認しつつ、地域住民が主体的に関わることができるよう、サポートをしている。
石徹白でも、飯田でも小水力発電導入には、水利権や関係機関との調整が必要なため、地域内での合意形成づくりは欠かせない。誰が主体者となっていくのかを見極め、そして地域の合意形成を丁寧につくっていくことが大切だ。また、小水力発電を何のために設置するのかをはっきりさせることも重要。観光資源としてなのか、エネルギー自給のためなのか、小さい単位での電力供給なのか。目的をはっきりさせて、地域での合意形成をはかっていくことが肝要だ。
5.小水力発電で地域づくり
かつて地域で維持管理していた小水力発電を地域の人たちの手に取り戻す取組は、地域づくりそのものだ。
以前の日本では、どこの農村地帯にも多くの水車が回り、電力や動力として利用してきた。昭和30年頃までは、都市部の大量な電気需要に応えるために、大規模な開発をし、ダムをつくっていった大水力発電と地域密着の小水力発電が両立していた。しかし、山間地まで電線が行き渡ることで、電力会社に主導権が移っていってしまった。効率が悪いと、分散型の小水力発電は廃止され、減少していった。
確かに小水力発電は、大都市の電力供給としての力には決してならない。しかし、地域で発電し、使う地産地消の再生可能エネルギーとして、見直しをするならば、そしてそれが地域住民の参画によって推進していくならば、新たな地域づくり」に大きく寄与できるはずだ。石徹白などではすでに始まっているのだから。
あなたの地域でも古くて新しいエネルギー「小水力発電」を地域づくりに活用してみませんか。
私は2007年から小水力発電の導入実験をし、あわせて持続可能な地域づくりを目指している岐阜県郡上市白鳥町石徹白(いとしろ)に調査に出かけた。説明していただいたのは、NPO法人地域再生機構理事の平野彰秀さん。

小水力発電の導入実験をしている「石徹白地区」は、岐阜県の福井県境にある、標高700メートルの盆地に位置する。縄文時代からの歴史を持ち、白山中居神社を中心とした白山信仰で栄えた村だ。明治まで神が仕える人が住む村として、どの藩にも属さず、年貢免除・名字帯刀が許され、独自に地域自治、文化を保ってきた。50年前には1200人ほどが住んでいたが、現在は1/4の約270人と過疎高齢化が進んでいる。
「なんとかしないと!」と危機感を持った住民たちは、2003年NPO法人やすらぎの里いとしろを設立し、「将来にわたっても、石徹白小学校を残すこと」を合い言葉に、地域課題解決に取り組んできた。持続可能な地域にしていくためには、「地域の自立」を目指し、地域産業づくりが必要と考え、小水力発電もその一環として、2007年から導入に向けて検討を始めてきた。石徹白には、白山に降る雪や雨の豊かな水量がある農業用水が張り巡っていた。冬は融雪、夏は野菜などの洗い場としても使われてきた、先人たちの遺産であるこの農業用水を活用して、水力発電に取り組んでいるのだ。
現在稼働しているのが、既存の農業用水沿いに導水路を設置し、そこにらせん型の水車をはめこんで発電するタイプ。この発電出力は、常時500W、最大800W。ここで発電した電気は、直流30V未満に変換し、道路を横断し、地元NPOの事務所の照明、冷蔵庫、テレビ等に使用されている。らせん型水車は、流量が多く、落差が低い場所に向いていて、ゴミがつまらないのが最大の利点だ。農業動力用として,以前は日本でも多く使われていた。設置費用は、約200万円。
現在、設置が完了し、稼働を待っているのが上掛け水車タイプ。これは、隣接する「白鳥ふるさと食品加工伝承施設(通称加工所)」の電力の一部を賄うために設置された。今後加工所は名産品のとうもろこしを使った加工品づくりに着手する予定だ。平野さんはこの水車を「地域の活性化のシンボルとしていきたい」と話す。出力常時750W、最大2200W。土木費用も含めて、設置費用約700万円。

石徹白地域では、将来電気軽トラを導入し、50Kw規模の発電所の設置をしたいと考えており、エネルギーの自給ができる地域を目指している。石徹白地域エネルギー自給可能性調査で、毎年およそ1200 万円が家庭での電気料金として、地域外に流出していることがわかった。車のガソリンや冬場の暖房の灯油などを含めるとエネルギー関連でさらに多くのお金が地域外に支出されている。そこで地域外にお金を流出させるのではなく、地域の資源を利用したエネルギー事業をつくることで今まで地域外に支出されていた金額、1200万円以上を地域に取り戻すことができるのではないかと地域では目論んでいる。
また、小水力発電の設置やメンテナンスは簡易な仕組みとなっているため、地域内の小規模事業者でまかなうことができ、地域の雇用にも寄与できる。例えば、上掛け水車タイプのブレード(はね)は、木製のため、万が一割れても、そこだけ取り替えれば済むことができる。
石徹白地域は小水力発電設置をきっかけとして、地域をあげた地域づくり、そして都市との交流が始まっている。具体的効果として、小水力発電を導入したことによって、小水力発電を目当てに石徹白に視察に訪れる人たちが増えたことだ。視察の際、活躍するのが「くくりひめ」という女性たちのグループ。(くくりひめの名前は、イザナギ命・イザナミ命が主祭神である白山中居神社の前にククリヒメの社があり、それにちなんで名付けた。くくりヒメは、イザナギとイザナミを仲直りさせたと言われる。調和と結合の神、和解の神、総てのものをくくり合わされるをご使命とされる仲直りの神様)。石徹白地域に住む女性たちが土地の旬の食材をバランスよく取り入れた、見た目、味も抜群なランチを提供する。小水力発電に視察に来た方々が、彼女たちのおもてなしと石徹白の自然や歴史に魅了され、石徹白ファンになっていっていくという。「地域ビジネスが地域ファンをつくり、地域ファンが地域ビジネスを支える」そんな実践モデルのひとつだ。ちなみに私と一緒に石徹白に視察に行ったひとりが石徹白をいたく気に入り、ちょうど募集をしていた加工所の求人に応募、子ども2人とともに家族で移住してしまった。また、今回説明をしていただいた平野さんも、石徹白の魅力にはまり、この秋から家族で岐阜市内から石徹白に引っ越しをしてくる予定だそうだ。「将来にわたっても、石徹白小学校を残すこと」という目標に石徹白に向かって、着実に向かっている。
3.小水力発電の全国の事例
現在、出力1000Kw未満の小水力発電は、長野、岐阜、富山などに約500カ所ある。京都市の嵐山、桂川の小水力発電所は、観光の名所渡月橋を渡る人々の足下を照らす照明のエネルギーとして供給されている。また、山梨県都留市では「小水力発電のまち」として、市役所前を通る家中川(かちゅうがわ)に開放型水車「元気くん」を設け、アピールしている。現在2台の「元気くん」が稼働中で、「元気くん」の電力は、日中は市役所の電力として使われ、市役所が閉庁する夜間や休日は、電力会社に売電している。平成21年度からは、「元気くん」が発電した電力に付加する「環境価値」を「グリーン電力証書」として、販売している
環境庁が2009年に実施した「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」によれば、1000kW未満の賦存量は、約629万kW(22,474カ所)となっている。参考までに、原子力発電1基は約100 万Kw。
そうした中で、環境モデル都市・長野県飯田市では、平成21年度環境省の小水力発電による市民共同発電実現可能性調査の委託を受け、いくつかの地点の水量や落差、発電設備の工事費や維持管理費のシュミレーション、年間発電量などを調査した。その結果、いくつかの有力な候補地が存在することはわかった。今後、環境調査とともに、地元住民の合意形成をはかっていき、事業化に向けて進めている。
また、新たな試みとして、市民出資で小水力発電事業を行う「立山アルプス小水力発電事業」が始まっている。小水力発電への市民出資事業としては、日本で初めてのものだ。市民のお金で日本国内の自然エネルギーを増やすことに取り組むおひさまエネルギーファンド株式会社が、富山県立山を水源とする小早月川の小水力発電所の設置への出資者を募集。発電で得られる収益の一部を出資者に分配金を還元していく仕組みだ。個人でも参加できることから、ひとりでは大規模で難しい自然エネルギーなどの導入や活用が、多くの市民の「意志ある出資」で、可能になっていく。志ある市民のお金「市民出資」により地域事業として実現することで、「21世紀の新しい地域 経済」の可能性を目指していく注目すべき動きだ。
4.小水力発電導入の課題
小水力発電の普及を妨げる要因の一つが、手続きの煩雑さだ。現状では、大型水力発電並の膨大な書類、手続きが必要だ。河川管理は国土交通省、農業用水は農林水産省、発電は経済産業省、などなど関係官庁がバラバラで、特に水利権の調整は煩雑だ。小水力発電を設置するための手続きの簡素化、規制緩和は急務だ。
「小水力発電」の水資源量1位の岐阜県と2位の富山県は、手を組んで、障害になっている水利権手続きの緩和などを国へ働きかける試みを始めている。また、岐阜県は、内閣府の総合特区に小水力を含めた新エネルギー振興に向けた総合特区の申請を予定している。
もう一つの要因が採算性だ。事業仕分けで国からの補助金が廃止されたため、初期投資に負担がかかり、せっかく事業を起こそうとしても二の足を踏んでしまう。現在、再生可能エネルギー法案が国会で審議されているが、小水力発電の売電価格は低く抑えられる可能性が高く、投資コスト回収ができるかどうか微妙なところだ。理想としては、小水力発電で発電した電力を長期間、発電に有利な価格で買い取ることを電力会社に義務づけることができるならば、小水力発電の普及が進んでいくことだろう。
しかし、設置の採算性だけを考えるのではなく、石徹白地域にように発電設備の設置や整備が地域の産業創出と見れば、新たな地域の収入源、雇用の確保が生じることとなる。小水力発電に適しているところは、水の落差がある山村や農業用水のある農村だ。いわゆる中山間地に、新たな地域産業が生まれることによって、働く場をつくり、地域住民の流出を防ぎ、新たな流入者を増やすことができる可能性も生まれる。
手続きや採算性の外部の課題とは別に、地域で「どこが主体としてなっていくか、どう主体を形成していくのか」という地域内部の課題も存在する。石徹白地域のケースでは、まず岐阜NPOセンターが「小地域のエネルギー自給モデルを構築するための実験・調査」をきっかけに石徹白に入っていった。当初、石徹白の歴史や文化を徹底的に調べ、様々な団体や寄り合いなどにヒアリングをして、地域性を理解していくところから取りかかった。そうした中で、NPO 法人やすらぎの里いとしろという地域再生に主体的に関わっている組織の存在と繋がり、協力体制をとる中で、調査段階から地域の方々と関わるようになっていった、しかし、住民全員が参加しているわけではないので、より多くの住民の理解を求め、事業を円滑に進めるために、自治会の会合において説明会を開き、自治会の賛同を得ることを心がけた。その後の様子は、上記で書いたとおりだ。そうした丁寧な主体づくりが「くくりひめ」「加工所」などの動きにつながっていった。
今後設置予定の飯田市でも、丁寧な地元説明会を開くとともに、あくまでも地域住民が主体であることを確認しつつ、地域住民が主体的に関わることができるよう、サポートをしている。
石徹白でも、飯田でも小水力発電導入には、水利権や関係機関との調整が必要なため、地域内での合意形成づくりは欠かせない。誰が主体者となっていくのかを見極め、そして地域の合意形成を丁寧につくっていくことが大切だ。また、小水力発電を何のために設置するのかをはっきりさせることも重要。観光資源としてなのか、エネルギー自給のためなのか、小さい単位での電力供給なのか。目的をはっきりさせて、地域での合意形成をはかっていくことが肝要だ。
5.小水力発電で地域づくり
かつて地域で維持管理していた小水力発電を地域の人たちの手に取り戻す取組は、地域づくりそのものだ。
以前の日本では、どこの農村地帯にも多くの水車が回り、電力や動力として利用してきた。昭和30年頃までは、都市部の大量な電気需要に応えるために、大規模な開発をし、ダムをつくっていった大水力発電と地域密着の小水力発電が両立していた。しかし、山間地まで電線が行き渡ることで、電力会社に主導権が移っていってしまった。効率が悪いと、分散型の小水力発電は廃止され、減少していった。
確かに小水力発電は、大都市の電力供給としての力には決してならない。しかし、地域で発電し、使う地産地消の再生可能エネルギーとして、見直しをするならば、そしてそれが地域住民の参画によって推進していくならば、新たな地域づくり」に大きく寄与できるはずだ。石徹白などではすでに始まっているのだから。
あなたの地域でも古くて新しいエネルギー「小水力発電」を地域づくりに活用してみませんか。